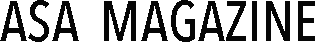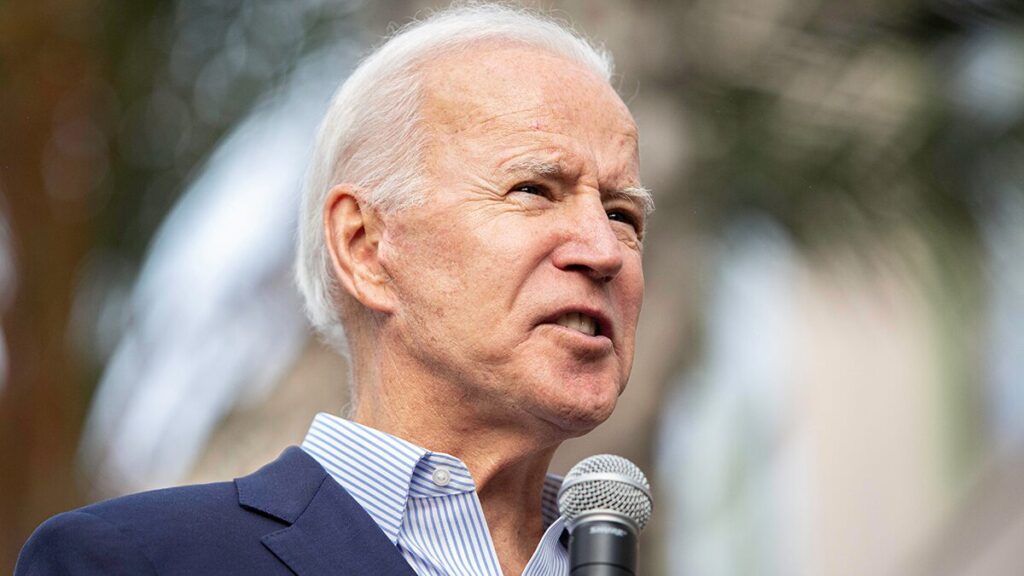「ずるずる出続ける鼻水」
多くの人が風邪を引くことにより鼻水が出たり、鼻が詰まったりといった経験をしたことがあるのではないでしょうか?
また、風邪以外にも花粉症やダニやほこりによるハウスダストなどのアレルギー、細菌やカビなどの菌が原因でも「鼻の不調」は訪れ、現代人を悩ませています。
これらは、副鼻腔に炎症が生じた場合に認められる症状です。副鼻腔とは、鼻の周囲にある骨で覆われた4つの空洞のことを指します。そんな副鼻腔における症状の予防に、大麻が役立つかもしれません。
2022年7月28日、大麻の日常的使用が副鼻腔症状の有病率の低さと関連していたことがアメリカの研究者らにより報告されました。
この研究は「National Health and Nutrition Examination Survey」における副鼻腔症状と薬物使用に関する20〜69歳の成人のデータ(2013〜2014年)を分析することにより行われました。
対象者数は2269名。副鼻腔症状として最も多く報告されたのは「鼻詰まり」と「臭いの変化」でした。
大麻を日常的に使用(過去30日以内に15回以上使用)している人の副鼻腔症状の有病率が45%であったのに対し、大麻を一度も使用したことがない人の有病率は64.5%で、日常的に大麻を使用している人では副鼻腔症状を発症する可能性が有意に低いことが明らかとなりました。
興味深いことに、時折の大麻使用(過去30日以内に15回未満の使用)と副鼻腔症状の有病率との間には関連性が認められませんでした。
なお、タバコの喫煙では副鼻腔症状の有病率が有意に高かったことも報告されました。
大麻使用と副鼻腔症状との関連が今回の結果に結びついたメカニズムについて、今後さらに研究を進めていく必要があると研究者らは述べています。
副鼻腔症状を認める代表的な疾患として「蓄膿症」が挙げられます。蓄膿症の正式名称は「慢性副鼻腔炎」であり、抗生物質が効かない例では手術となり、しかも術後に再発することも珍しくありません。
もしかしたら日常的な大麻使用は、そんな辛い蓄膿症の予防にも有効かもしれません。